はじめに
場面緘黙は、特定の状況や環境で話すことが難しい状態を指します。
この記事では、場面緘黙の特徴や診断基準から、効果的な支援方法、専門家からのアドバイス、さらにそらまめキッズでの活動までを詳しく解説します。

場面緘黙の基礎知識
場面緘黙の概要と特徴
場面緘黙は、子どもたちが特定の環境で言葉を発することが困難になる一方、自宅や安心できる環境では普通に話すことができるという特徴があります。この状態は、単なる「恥ずかしがり屋」とは異なります。
リラックスできても話せない状態が続き、1か月以上発話がない場合は、支援の開始をオススメします。
・発生率:0.2~0.7%で、やや女児に多い
・発症時期:通常5歳未満で、社会的な交流や発表などの機会が増える入園入学後に、症状がはっきりしてくる。
場面緘黙になる原因として、『親の育て方のせい』ではありません!!
生まれつき危険に対して敏感な気質を持つ子が多いと言われています!
大切なことは、もう一度!
親の過保護やしつけなどと考えるのは間違いです!!
(※ただし、症状の改善には保護者の理解や子どもへの接し方の工夫は必要です◎)
症状と診断基準
場面緘黙の子どもの特徴
・家族以外と話せない
・特定の友だちと小さい声で話す
・音読など決まったセリフは話せる
・話せないが元気で活発な子もいる
など子どもの状態は様々です。また、発話だけではなく、「感情表現」や「動作」ができにくい子もいます。
・表情がとぼしい
・自分の気持ちを出しにくい
・動きがぎこちない
・人の目が気になる
・声を聞かれること、注目されることが怖い
家族の前では「うるさいくらいしゃべる」「よく笑っている」のに…
園や学校では「本当の自分」が出せずにつらい思いをしていることもあります。
診断基準
DSM-5では、少なくとも症状が1か月以上続き、学校や社会生活に支障をきたす場合などに診断されます。
(DSM-5:米国精神医学会が作成した精神疾患の診断基準をまとめたガイドライン)

支援方法
安心感を高める環境づくり
まずは、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが大切です!
1.非言語的なコミュニケーションの活用:アイコンタクトやジェスチャーを通じた意思疎通。
もちろん言語的に「〇〇ちゃんが大好き」などと言葉にして伝えるのも◎
2.安全基地の提供:信頼できる大人や環境を確保。
楽しくホッとできる家庭環境を心がけましょう♪
3.プレッシャーをかけない接し方:子どもが自然に話せるようになるのを待つ姿勢。
声を聞かれることを不安に思う子どももいます。話すようにプレッシャーを与えるのはNGです(._.)
家庭と学校での具体的な支援策
家庭での取り組み
・子どもの1番の理解者になりましょう!
・正しい知識と適切な関わり方を知りましょう!
・「できること」に目を向けて、さりげなく褒めましょう!
そらまめキッズのInstagramでも理解者になるポイントをお伝えしていますので、ぜひご覧ください♬
→【場面かんもく 一番の理解者にわたしは なる!】
学校での支援
・家庭と学校での情報共有、連携を図りましょう!
支援方法について、家庭と学校で話し合えていない場合も多い為、連絡帳など使用してこまめに情報交換を行いましょう!
・話すことを強要せず、代わりにカードやタブレットを使ったコミュニケーションを図りましょう!

専門家からのアドバイス
1.子どもを責めない:発話できない理由を本人のせいにしないこと。
話さないのではなく、話せないということを理解しておきましょう◎
2.ポジティブな体験を積む:成功体験を重ねることで自信を育む。
楽しく自信をつけながら、今できることからスモールステップでチャレンジしていきましょう。
3.専門家の力を借りる:必要に応じて病院や施設に相談する。
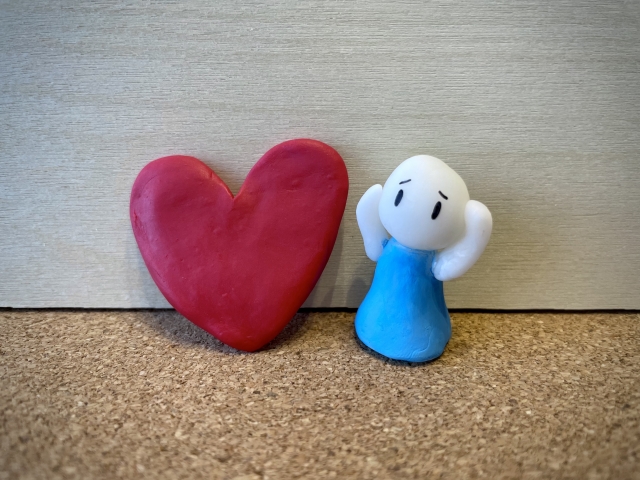
そらまめキッズでの活動
そらまめキッズでは、年に1~2回、場面緘黙のある子のご家族、園や学校の先生、場面緘黙について学びたい方を対象に「場面かんもくの集い」を行っています。
そこでは、場面緘黙の基礎知識を学び、スモールステップ表をグループで作る演習もあり、保護者同士の情報交換や、活発なディスカッションも行われています♪
ぜひ、興味のある方はそらまめキッズのInstagramをフォローして、情報をお待ちください(^^♪
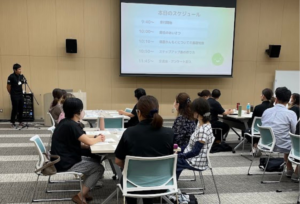
おわりに
場面緘黙への理解を深めることは、子どもたちが安心して自分を表現できる環境を築く第一歩です。この理解が広がることで、子どもたちは少しずつ自分の気持ちを伝え、自信をもって社会とつながる力を育むことができます。
そらまめキッズは、そのための懸け橋として、ご家族や教育者の皆さんとともに歩み続けたいと思います♪
 Instagram
Instagram
 TikTok
TikTok
 Note
Note
 Facebook
Facebook










